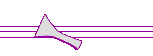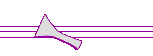|
|
 |
| 幼少の頃より、母・民謡家の指導を受け、民族音楽の研鑽に努む |
| 昭和50年東芝EMIレコードと≪白瀬孝子≫の芸名で専属契約、本格的活動にはいる |
| 昭和51年 大阪・梅若梅朝と婚姻、梅若会副会主として会務を補佐 |
| 昭和52年 東芝EMIより≪白瀬孝子≫愛唱LP発売 |
| 昭和53年 東芝EMIより≪梅若梅朝・白瀬孝子≫愛唱LP発売 |
| 1984年より<国際民族インターナショナル大会>副団長として参加活動 |
| <国際民族インターナショナル大会>ソウル・タイ・マレーシア |
| <1986年アジア大会><1988年ソウル・オリンピック>参加公演 |
| 1996年 イギリス・ロンドン他公演(大阪府派遣) |
| 平成7年 梅若会・二代目会主継承≪梅若孝子≫と改名 |
| 民謡・おはやし・踊り・太鼓・三味線等指導、定期公演会開催 |
| 平成10年 (社)全大阪みんよう協会本部・事務局補佐就任 |
| 平成12年10月 東芝EMIよりコロムビアレコード会社に移籍 |
|
 |
失われたものを求めて |
| 日本民謡梅若会 二代目 |
梅 若 梅 朝(孝子) |
 |
| |
現代日本は、じつに乾燥しきってしまい、
ひび割れをおこし、少しの湿り気さえなくなり、
資源浪費と環境破壊をともなう「おいしい生活」技術文明は限界にたっしている。
科学万能主義の日本は、いつのまにか「感じる」ことを一段下に見下ろすようになり、
本当の自分の感情を忘れるという「魂の非常時」を迎え、人間的な潤い、
心も情さえもない社会をつくりあげてしまった。
田植えや盆踊り、祭礼など、日々の生活と労働のなかで、
おおぜいの人々の間に歌いつがれてきた民族音楽。
民族音楽とは民謡やわらべ歌、民族芸能や民族宗教(民間信仰)などの音楽を指し、
民族文化の一環をなす。
とりわけ日本人が長い歴史の中で自然に培ってきた民謡は
文字や楽譜をなかだちとせず、
口から耳へと直接に伝承された唄であり、
そのひと唄ごとに本来の用途と人々の信仰があった。
戦後文化人がもっとも蔑視したものが演歌的な抒情、
義理人情の世界、そして情緒的な反応であった。
そして今、総カラオケ、デジタル化、乾ききってしまった現実が、
みごとに乾いた社会をつくりあげ、乾いた『こころ』をつくりあげてしまった。
日本の文化も、その本来の二元性−自然と文化の呼応の関係を見失ってしまい、
自然を切り棄て機械化してしまった。
私たちは思想とか、瞑想によって、民族音楽の世界に近づくのではなく、
身体によって、身心を投げ出して、この世界に没入していく。
すなわち飛び込む、没入する、浸り切る。
そこで反転して自然とともに自然の創造活動にただひたすら参与し、
自然の本質と人間性を表現していく。
つまり聞く唄と歌う唄、その区分のなかで、私たちは唄を自分の身近に引き寄せ、
そして日常の生活のなかで歌を発することができる、
≪心偈=こころうた≫を求めつづけることにより、
心も情さえも冷えきった社会に少しでも湿り気、人間的な潤いを
与えていくことができるのではと信じながら歌い続ける。 |
|